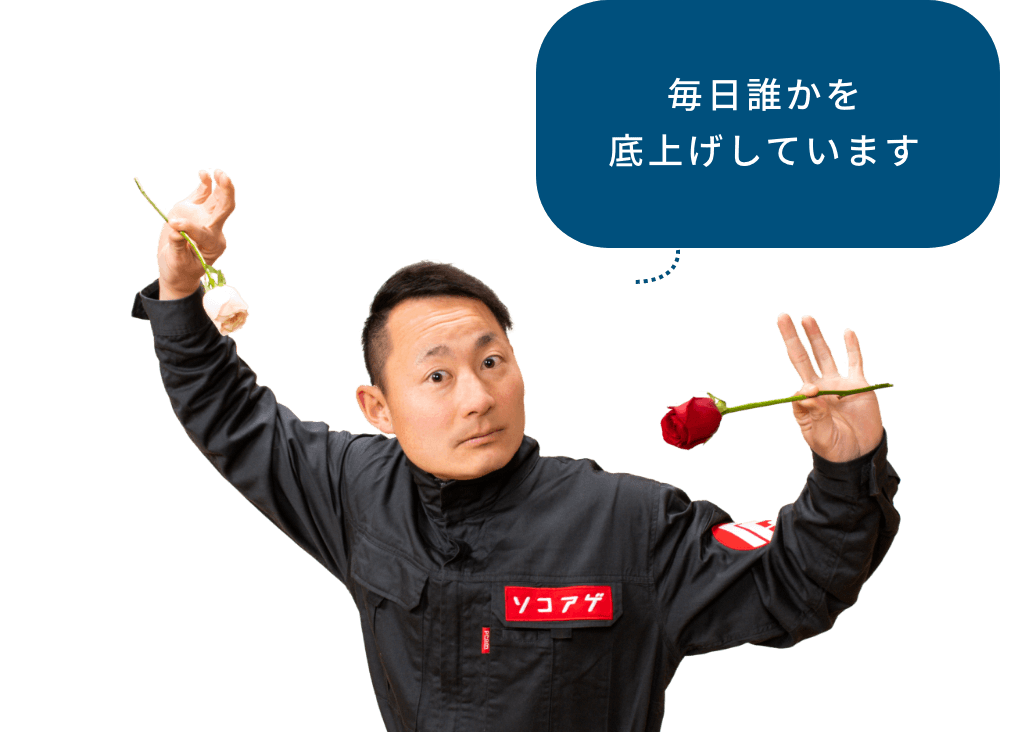実習受け入れを通してwell-beingについて考えてみた

こんにちは、なるです。
前回のブログで触れた今年6,7月の2週間半実施した武蔵野大学well-being学部の2年生20名の気仙沼実習受け入れをしたお話し。
改めて前回のブログを読んでみて、時間が経ったらもう少しすっきりするかと思いきや、あまり考えていることがアップデートされてないことにも気づきましたw
これも気づきです、そう受け止めよう。
そういう意味ではなかなか答えの出ない貴重な問いをもらったんだなと実感。
ここ数ヶ月ずっと考えていることは「わたしのウェルビーイング」と「わたしたちのウェルビーイング」のバランスについて。
言葉だけでもなんとなくイメージはつくと思いますが、わたしのウェルビーイングを優先して物事を進めていこうとすれば、もしかして他者に対し迷惑をかけたり嫌な思いをさせたり時には傷つけたりするかもしれない。
とはいえ社会全体を俯瞰して見るとわたしたちのウェルビーイングを重んじるべきという風潮のもと、わたしのウェルビーイングがないがしろにされてしまうことも圧倒的に多く見られます。いわゆる”空気を読みなさい”とたしなめる言葉が良い例ですね。
自分の活動を振り返っても、個々の失われてしまった”わたしのウェルビーイング”を取り戻すため、自己を見つめ直し、自分の思いを表現し、お互いに受け止め合える安心・安全な空間づくりに努めていることが多いですし、とても大切なことだと思っています。
一方で、わたしのウェルビーイングだけを持っていわゆる社会や組織に触れていくと、そのギャップに悩み苦しむことも事実です。
この間にとても重要な時間の積み重ね方があると思っています。
この問いがまさに僕の探究テーマですが、一つの要素として思うのは、
「わたしのウェルビーイング」からなる表現を受けとめる側の「わたしのウェルビーイング」も同時にしっかりと表現されること、そしてそれをひたすら「対話」によって調和していくことなのかなと。
調和という言葉には「和し合って、美しくまとまっている状態」という意味があります。
美しさをどうとるかは人それぞれですが、お互いの意見や思いが一致する必要は全くなく、そのどちらもこの場において存在しているということを良しとして、それをどう受けとるかも個々に委ねられている感覚なのかなと。
もう少し言うと「ウェルビーイングのつくりかた」という本の中にある「ゆらぎ、ゆだね、ゆとり」も存在している場であるということかと思っています。
まとまりのない文章となってしまいましたが、これからも「わたしのウェルビーイング」と「わたしたちのウェルビーイング」の美しいバランスを見つけていけるよう対話し続けていきたいと思います。
写真は今回の実習の1コマ、自然の中での対話の風景。


成宮崇史
認定NPO法人底上げ 理事
気仙沼で中高生の伴走支援、多世代のチャレンジのサポート、学びの場づくりなどを行っています。最近は自治会のロールモデルづくりを目指していそいそと頑張ってます。久しぶりの坊主がとにかく楽で気に入ってます。